最近、地震のニュースを見るたび、こう思いませんか?
「もし今、大きな地震が来たらどうしよう…」
すぐに来ることはないだろうとたかをくくって、対策を後回しにしていませんか?
そう考えている方は、恐らく明日も明後日も対策することはないでしょう。
地震対策を始めるタイミングは、まさに今。
この記事を読むことをきっかけに地震対策に踏み出してみてはいかがでしょうか?
「対策しなければいけない」と思っても、「何から始めたらいいかわからない」「お金がかかりそうだし、なんだか難しそう」と、つい後回しになりがちです。
でも実は、ホームセンターなどで手軽に揃えられるグッズを使った「小さな対策」が、いざという時に家族を守る絶大な効果を発揮するんです。
この記事では、誰でも簡単にできて、なおかつ「大きな効果が得られる地震対策」だけを厳選してご紹介します。読み終える頃には「これなら今すぐできる!」と、行動に移せるはずです。
・地震対策をする理由を知りたい方
・地震対策のやり方がわからない方
・耐震用品の選び方がわからない方
・この機会に地震対策を始めたい方
なぜ地震対策が必要なのか?
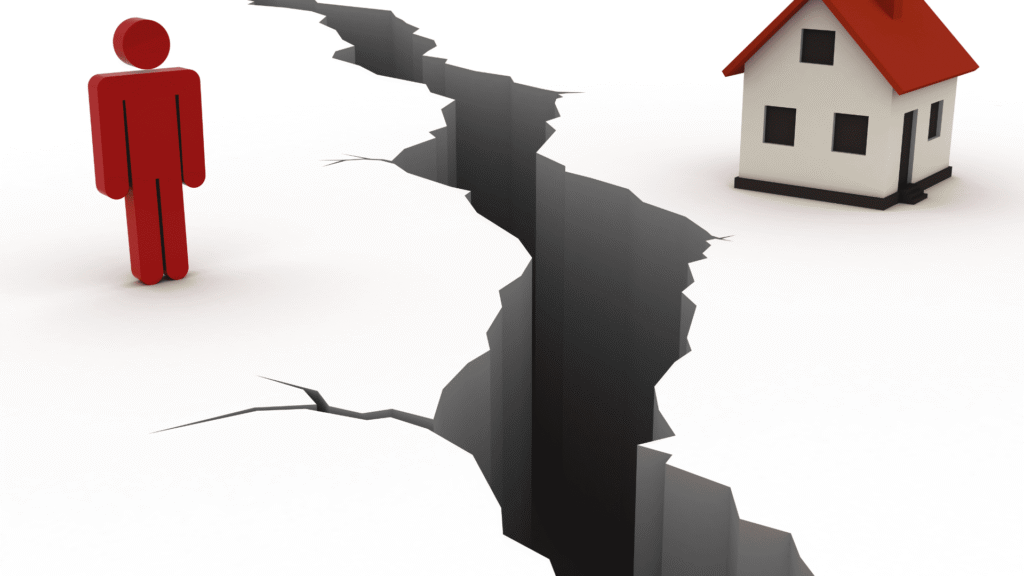
「いつかやろう」と思いがちな耐震対策。しかし、その「いつか」は一生来ないでしょう。
なぜ、すぐ始めるべきなのか、その明確な理由を2つの事実からお伝えします。
・日本は世界有数の地震大国
・30年以内に80% 南海トラフ地震の脅威
日本は世界有数の地震大国
まず大前提として、私たちが住む日本は世界的に見ても非常に地震が多い国です。
世界のマグニチュード6以上の地震の約2割が、この日本の周辺で発生していると言われています。
つまり、日本に住んでいる以上、地震は決して他人事ではなく、常に身近にあるリスクなのです。だからこそ、日頃からの備えが、いざという時に家族の命運を分けることになります。
30年以内に80% 南海トラフ地震の脅威
日本が地震大国である中でも、特に警戒が強まっているのが「南海トラフ地震」です。
これは、東海から九州にかけての広い範囲で、甚大な被害が想定されている巨大地震です。
この南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は「70%~80%」と、
非常に高く予測されています。
これは決して遠い未来の話ではなく、私たちの世代、あるいは私たちの子どもたちの世代で大地震を経験する可能性が極めて高いということです。
この数字は、耐震対策が「念のため」ではなく、「必須」の備えであることを示しています。
耐震対策をしないとどうなる?身近に潜む2つの大きなリスク
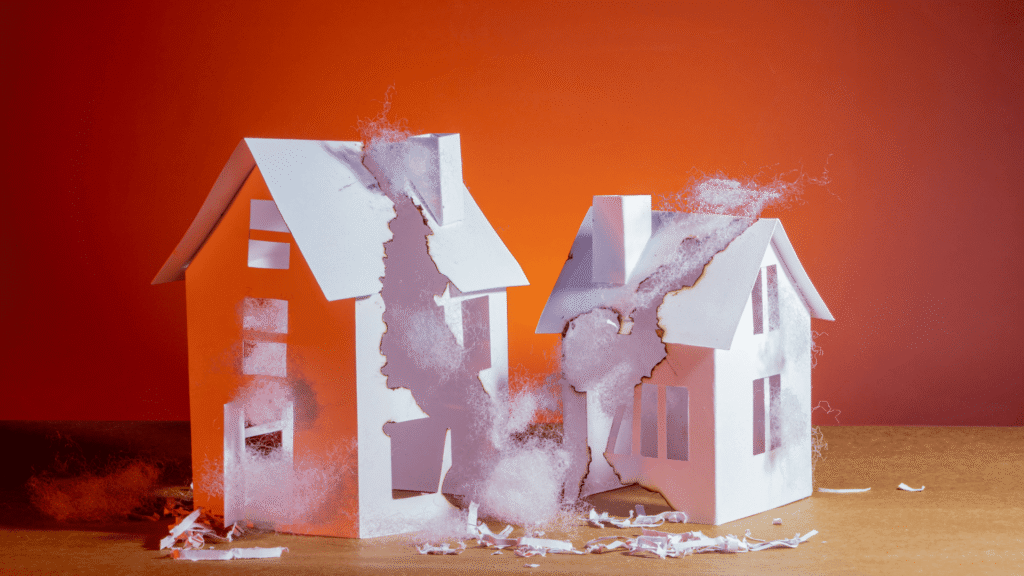
地震対策の目的は、大きく分けて「ケガの防止」と「避難経路の確保」の2つです。
もし対策を何もしなかった場合、家の中はどのように危険な場所へと変わってしまうのでしょうか。
・事故・けがのリスク
・避難阻害のリスク
事故・けがのリスク
過去の大地震では、建物の倒壊だけでなく、
家の中での事故で命を落としたり、大怪我をしたりした方が非常に多くいました。
寝ている間に背の高いタンスが倒れてきたら?
大型テレビが台から滑り落ちてきたら?
食器棚からガラスや陶器の破片が飛び散り、床に散乱したら?
特に、停電で真っ暗な中、裸足で逃げ惑う状況では、普段は何気なく置いている家具や食器が、命を脅かす凶器に変わります。対策をしないということは、こうした危険と常に隣り合わせで生活していることと同じなのです。
避難阻害のリスク
大きな揺れが収まった後、次にすべきことは安全な場所への避難です。
玄関や部屋のドアの前に大きな家具が倒れて、出口を完全に塞いでしまったらどうなるでしょうか。
もし火災が発生していた場合、逃げ遅れて命を落とす危険性が一気に高まります。
無事に避難するためには、家の中の「逃げ道」を常に確保しておくことが絶対条件。耐震対策を怠ることは、いざという時の命の道を自ら塞いでしまうことに繋がりかねません。
耐震用品の紹介と選び方

「よし、対策しよう!」と決めたら、次はグッズ選びです。
ここでは、耐震用品の具体的な選び方のポイントとあわせて、目的別におすすめの耐震用品を分かりやすく解説します。
・家具の転倒防止
・小物関係の破損防止
・ガラス飛散防止
家具の転倒防止
家具の転倒防止は地震対策の基本です。事故・けがを防ぎ、避難経路を確保する役割があります。
一番簡単にできて、なおかつ効果も高いので、ぜひ対策を進めましょう。
突っ張りポール
部屋の天井と家具の天井の間を力強く突っ張ることで、家具が倒れるのを防いでくれる定番アイテムです。
壁や天井に穴を開ける必要がない為、簡単に対策することができます。
また、賃貸物件でも可能な対策となっております。
【選び方のポイント】
まず、設置したい場所の「家具から天井までの高さ」を正確に測りましょう。商品に〇〇mm~〇〇mm迄対応と書かれているので、必ずその範囲内のものを選びます。
設置する際は、部屋の天井の裏に柱(下地)が入っていることを確認してください。
前面ストッパー
家具の手前側の底に敷くだけで、家具全体が壁側へ少し傾き、重心が後ろにずれて倒れにくくなる器具です。
こちらも簡単に設置できる為、突っ張りポールと組み合わせて使われることが多いです。
家具の横幅に合わせて、十分な長さのものを選びましょう。長い分にはハサミで簡単に切れますので、長さ調整して使用しましょう。
小物関係の破損防止
小物関係にも対策が必要です。地震の振動で棚やテーブルから落ちたときに破損する場合があります。
破損したときの破片が飛び散れば、事故やケガに繋がります。
避難時にも邪魔になってしまいますので、高価なものはもちろんですが、小さなものまでしっかり対策するようにしましょう。
耐震ジェル(耐震マット)
テレビやパソコン、花瓶などの底に貼るだけで、吸盤のようにピタッと固定できるジェル状のマットです。
貼るだけなのに驚きの粘着力で、揺れによる落下を強力に防ぎます。
【選び方のポイント】
設置したいモノの「重さ」を確認し、製品に表示されている「耐荷重」がそれを上回るものを選びましょう。一回とりつけると数か月から数年間吸着が可能ですが、もし吸着力が落ちてきたら、水洗いで復活しますので、再度貼り付けましょう。
L型金具固定・ベルト装着
より強力に固定したいなら、ネジを使うタイプが最適です。
L型金具は家具と壁を直接繋ぐため、強度が高く、地震対策に非常に有効です。
また、直接つながず、間にベルトを挟むことによって、壁との距離があった場合でも固定が可能です。
【選び方のポイント】
金具は少しの振動で破損しないように、ある程度厚みのある金具を選びましょう。ベルトタイプは金具とセットになっているものが販売されているので、そちらを購入しましょう。これらは壁にネジで固定するため、壁の裏側にある柱(下地)の場所を確認する必要があります。
扉開き防止金具
食器棚や吊り戸棚の扉に付けておくと、
揺れを感知した瞬間に扉をロックしてくれる賢いアイテムです。
中のお皿やグラスが飛び出して散乱するのを防ぐことができます。
【選び方のポイント】
自宅の棚が「開き戸」か「引き出し」か、扉の種類に合ったものを選びます。また、扉の内側に取り付ける本格的なタイプと、外側に貼るだけの簡易タイプがあるので、取り付けの手間や見た目を考慮して選びましょう。
ガラス飛散防止
窓や食器棚のガラスが割れても、破片が飛び散るのを防ぎます。
破片は通常時はもちろん、停電時に起きると非常に厄介です。しっかり対策をしましょう。
ガラス飛散防止フィルム
窓ガラスなどに貼る透明なフィルムで、
万が一ガラスが割れても破片がフィルムに付着したままになり、飛散を防いでくれます。
見た目をほとんど変えることなく、ケガのリスクを大幅に減らせる優れたアイテムです。
【選び方のポイント】
自宅の窓ガラスが「ツルツルした透明なガラス」か「凹凸のあるすりガラス」かを確認し、それぞれ専用のフィルムを選びましょう。また、UVカットや断熱、目隠しなど、防災以外の付加機能がついた製品も多いので、目的に合わせて選ぶと一石二鳥です。
耐震対策とあわせてやりたい!そのほかの防災対策とは

ここまで、地震対策に焦点を当てて説明して参りました。
ここからは地震対策以外の防災対策を一部紹介しておきます。
・水・食料の備蓄
・乾電池・カセットガス
・防災かばん
・現金
・防災アプリ
水・食料の備蓄
まずは生きるために不可欠な水と食料です。
目安は家族の人数 × 最低3日分。可能であれば1週間分用意してください。
水は1人1日3リットルが基準です。非常食は防災用の特別なものでなくても、普段から食べているレトルト食品や缶詰、お菓子などを少し多めに買っておき、古いものから消費して新しいものを買い足す方法で、無理なく備蓄することができます。
乾電池・カセットガス
停電に備えて、懐中電灯や防災ラジオを動かす乾電池を備蓄しましょう。
サイズ(単三、単四など)を確認し、予備を必ず用意する必要があります。
また、ガスが止まってもお湯を沸かしたり温かいものを食べたりできるカセットコンロとカセットガスは、必須アイテムとなりますので、必ず準備しておきましょう。
防災かばん
避難が必要になった時に、貴重品や必需品をまとめてすぐに持ち出せるようにしておくのが「防災かばん」です。
中身は、水や食料、簡易トイレ、ラジオ、救急セット、常備薬、軍手、モバイルバッテリーなどを基本に、家族構成に合わせて必要なものを追加しましょう。
玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に置いておくのがポイントです。
現金
災害時は大規模な停電が発生し、クレジットカードやスマートフォンの決済機能が使えなくなる可能性が非常に高いです。
現金がないと、販売してあるものが買えない為、小銭も含めて用意しておきましょう。
防災アプリ
今やスマートフォンは重要な情報源です。
緊急地震速報を受け取ったり、避難所の場所を確認したり、家族の安否情報を登録したりできる「防災アプリ」をインストールしておきましょう。
多くの自治体が公式アプリを提供しているほか、
ハザードマップが見られる機能を持つアプリもあります。
自分に合ったものを探し、使い方に慣れておきましょう。
まとめ

今回は、地震対策の必要性から、初心者でもすぐに始められる具体的な耐震用品の選び方、そしてその他の防災対策までをご紹介しました。
南海トラフ地震という大きなリスクが迫る中、
耐震対策はもはや「特別なこと」ではありません。
家具を一つ固定する、ガラスにフィルムを一枚貼る。そんな小さな行動の一つひとつが、万が一の時に家族の命を救うことに直結します。
この記事でご紹介したグッズは、お近くのホームセンターなどで手に入ります。まずは、一番気になった場所の対策からで構いません。今日できる小さな一歩を踏み出して、大切な家族とのかけがえのない日常を守りましょう。
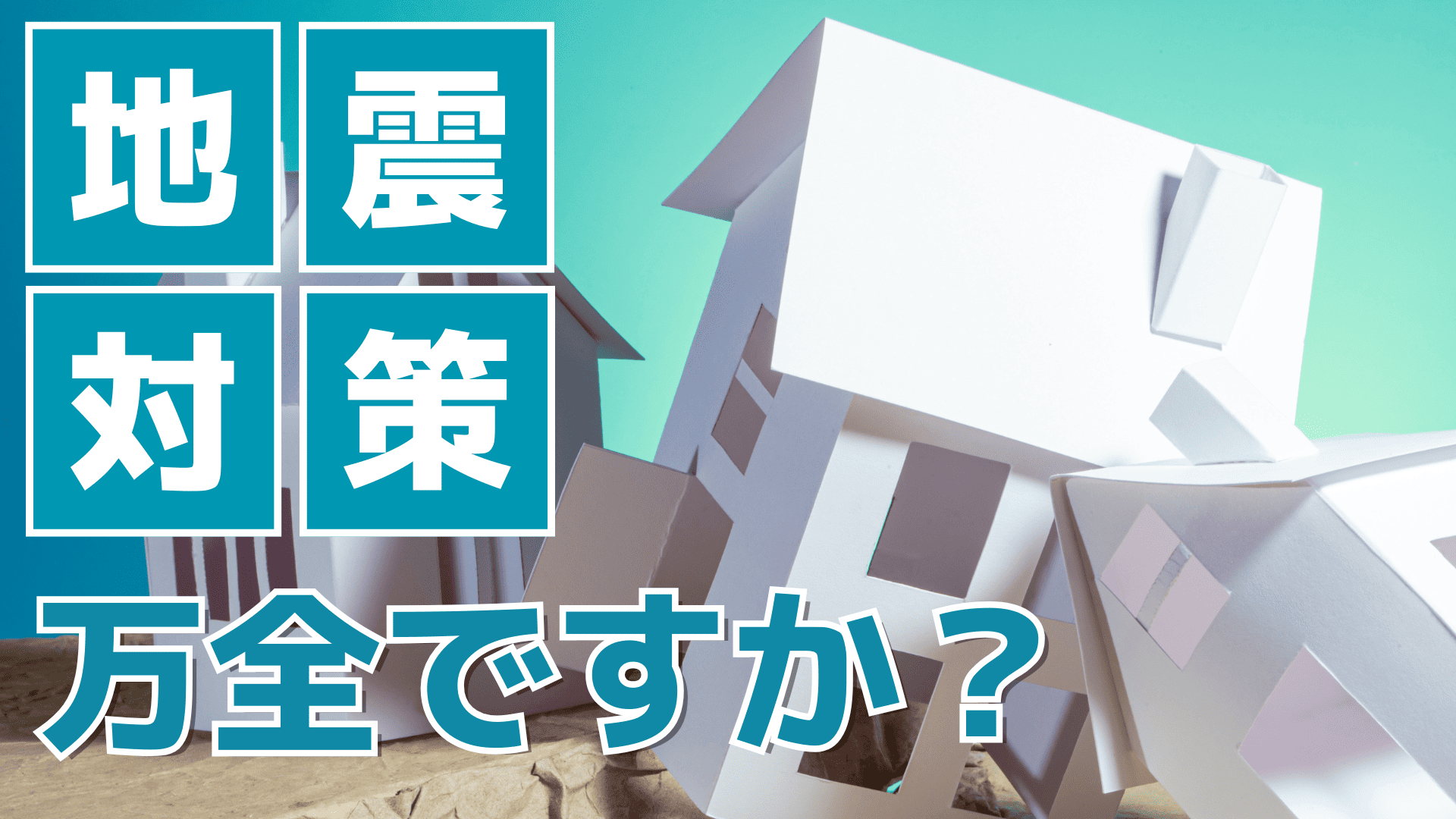








コメント