AIで本当に仕事がなくなるのか?
「AIが仕事を奪う」とよく言われますが、実際にはすべての仕事がなくなるわけではないことが多くの調査でわかっています。
ゴールドマン・サックスの2023年の調査では、世界で約3億人分の仕事がAIで自動化される可能性があるとされる一方、ほとんどの仕事は一部の作業のみが自動化されるにとどまり、AIは仕事を完全に奪うのではなく、人間を補完する存在になると指摘されています(AIの最新の波、3億人の雇用に影響も ゴールドマン・サックス – CNN.co.jp)。
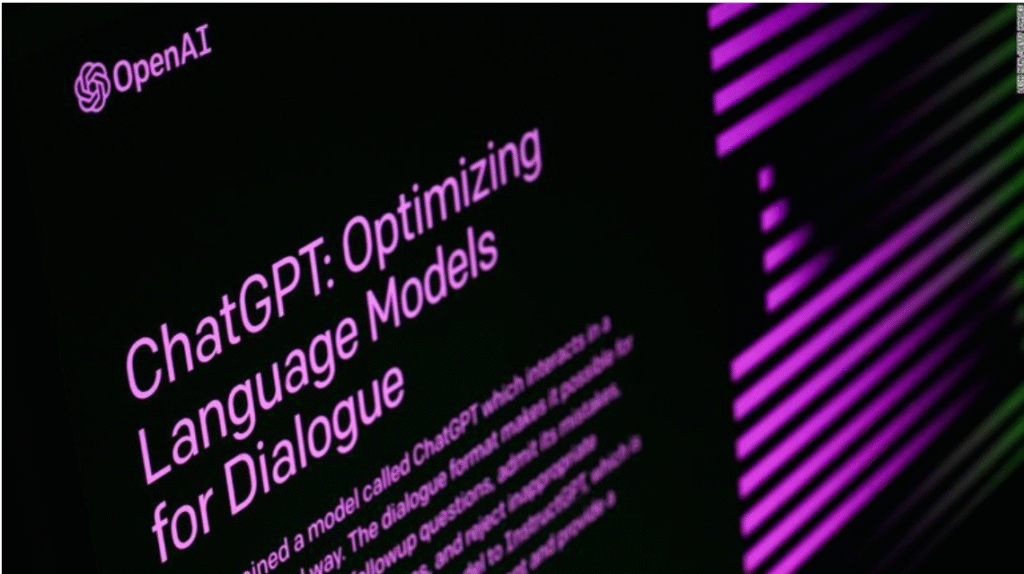
国に例えるなら、AIは「国の優秀な官僚」のようなものです。
国民(社員)の代わりに一部の事務処理を効率化しますが、国そのものを動かす意思決定や新しいルールづくりは、人間がいないと成り立ちません。
AIは、国を支える“補助役”としての存在だと考える方が現実に近いのです。
AI導入が引き起こす「経営者の葛藤」
AIを導入すれば、人件費を削減できる可能性があります。
一方で、従業員の仕事を奪ってしまうのでは?という葛藤を抱く経営者は多いです。
経済産業研究所(RIETI)の岩本晃一氏は、パーソル総合研究所の調査で次のように指摘しています。
「なくなる仕事」とは、AIで完全に代替可能なルーティン作業(例:企画書・報告書の作成、プレゼン資料の作成など)。
一方で「なくならない仕事」とは、AIでは代替できない予測困難な仕事、すなわちプログラム化できない業務。
例えば、前例のない株取引の判断やニュース番組での独自解説、政治家や企業の要職など、高度な判断や創造性が求められる領域は依然として人間にしかできないとされています。
つまり、AI導入で仕事がゼロになるのではなく、「仕事の内容が変わる」ケースが多いのです。
国の例えでいえば、新しいテクノロジーで官僚が効率化されることで、一部の役割が変化し、国民は別の重要な仕事を担うようになる、というイメージです。
今のうちに取れる対策とは?
将来の不安を減らすには、今から備えることが大切です。
- AIに任せられる作業を見極める:ルーティンワークはAIに任せると効率化が進みます。
- 社員の役割を新しい価値にシフトさせる:企画力や対人コミュニケーションなど、AIが苦手な領域に強みを移す。
- AI導入を“リストラ政策”ではなく“国を強くする政策”として考える:役割を再配置することで、従業員と会社の両方が成長できます。
このように考えると、AIは雇用の敵ではなく、未来に備えるための「強力なパートナー」として捉えられるはずです。
AIを正しく知ることが第一歩
不安の多くは、AIの実態を知らないことから生まれます。
まずは正しい知識を得ることが、未来に備える第一歩です。
参考記事:【AIの教科書】AIとは?いまさら聞けない基本のキ
AIを理解すれば、「怖い存在」から「頼もしい味方」に見方が変わるかもしれません。
まとめ:AIは脅威ではなく、未来への準備の味方
AIによって一部の仕事は変わる可能性がありますが、完全に仕事がなくなるわけではありません。
今のうちにAIと人間が共存できる働き方を考えれば、将来に備えることができます。
AIはリストラの道具ではなく、会社を強くするための新しい武器です。
「今ならまだ間に合う」と考え、行動に移すことが何よりの対策です。
“`

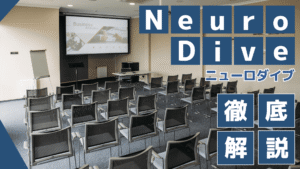




の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155-300x233.jpg)


コメント