★理解度を深める
漠然とした理解は定着しない。
これが一番大事なポイントである。
人が何かをインプットしたときに記憶に残るかどうかはこれで決まる。
例えば本を読むとしよう。
全ての文章を読んで理解して解読できたとしてもまだスタートラインなのだ。
その本で紹介していたこと、定説、理論について、
なぜ?と聞いて理解度をどんどん深めていく必要がある。
表面だけをなぞっただけだと、それは他人の言っている意味を理解しただけ。
真の理解とは、その表面に見えている事象に対して、
なぜそうなるのかを限界まで考え抜いた先に、
あっ、この人はこの事が言いたかったんだという本質の部分にたどり着く。
それが本当の理解するという意味だ。
そうやって得た知識は一生忘れないだろう。
【1】アウトプット
真の理解は頭の中だけでは、絶対に完結しない。
頭でどんだけ完璧に理解したと認識していても、
現実のアウトプットができていないということは、
体が理解していないということだ。
真の理解とは、脳と体が全て理解しできるようになったときに訪れる。
また、アウトプットは知識の定着にも素晴らしい効果を発揮する。
アウトプットは思い出すという行動とセットになる、
そのため、その情報が脳に必要なことだと認識させることにより、
記憶の引き出しの大事な部分に収納することができるのだ。
【2】反復
繰り返す=記憶。
脳は大事な情報といらない情報を仕分けしている。
何度も使われる情報は必要と感じて記憶として定着されるが、
たまにしか使わない重要度の低い記憶に関しては、
雑に扱うため、記憶として定着しない。
そのため、反復作業が大事なのだ。
何度も何度もその情報を登場させることにより、
この情報はめちゃくちゃ使う情報なんだと脳に覚えさせる。
そうすると自然と覚えられるのだ。
また、その際に一方向からだけだとすぐに飽きてしまうため、
様々な角度からのアプローチが望ましい。
同じ事象でも、見る角度によって見え方も変わってくる。
常に様々な視点から物事を見ることを忘れないようにする。
【3】比較
比較すると情報の輪郭がはっきりする。
例えば、ここにリンゴがある。
これを見て赤いと感じるだろう。
ただそれはまだ、漠然とした情報なのだ。
確かに赤いがそれがどれぐらい赤いかまで、頭が考えていないのだ。
今度は横にみかんを置く、当然オレンジ色だ。
りんごとみかんを横に並べて比較する、
すると今までのリンゴの赤色がどれぐらい赤いのかがわかる。
比較対象がないと、人の脳は深度を測れないのだ。
みかんが横にあることによって、リンゴが当然赤いのだが、
みかんと比べると、めちゃくちゃ赤いとなるのだ。
【結論】学んだものは自分の外に出す。
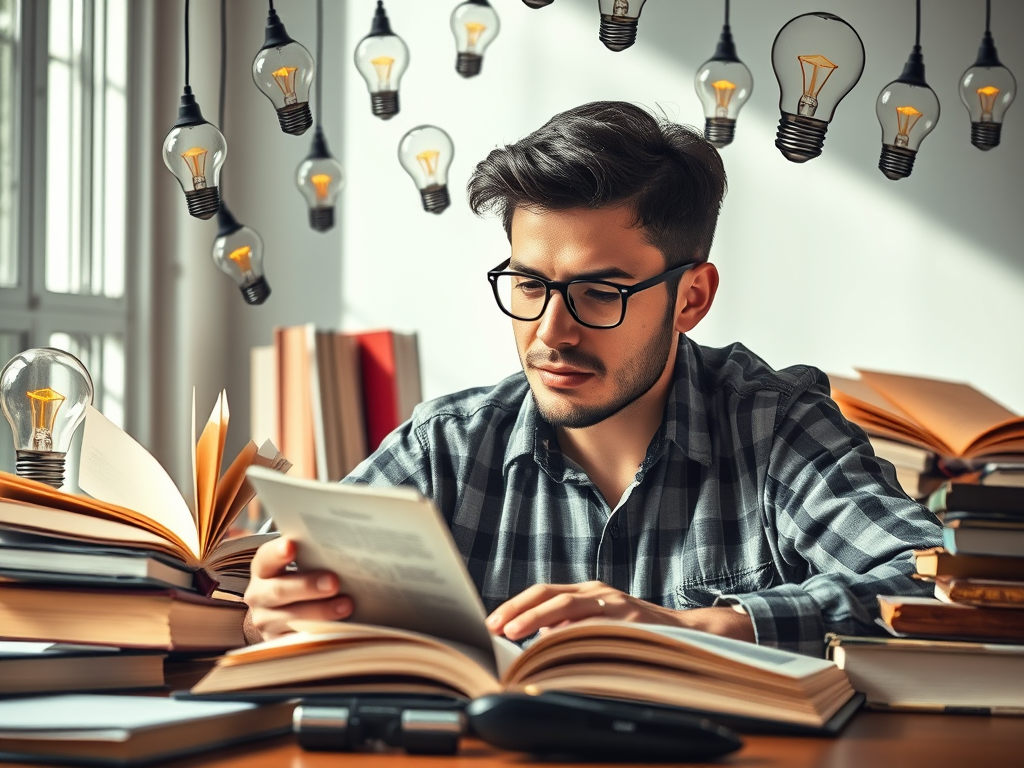
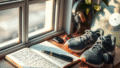

コメント